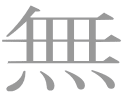 |
|
あんたが、世界の色だったんだ 白黒の世界にたった一色、射した色だったんだよ 俺も初めてそれを知った―――あの日。 |
|
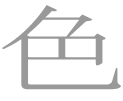 |
|
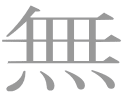 |
|
あんたが、世界の色だったんだ 白黒の世界にたった一色、射した色だったんだよ 俺も初めてそれを知った―――あの日。 |
|
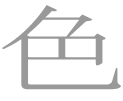 |
|
| 01:疾走する猫 02:忘却者の問 03:掌の上の夢 04:漆黒に踊る 05:喪失の爪痕 06:無色の世界 07:微睡みの猫 08:何度恋する 09:目覚の接吻 10:忘れ得ぬ色 |
01. 疾走する猫
奔る。
汗が流れるのが分かったが、それは置き去りにされて後ろに流れる。
それだけのスピードを持って足を動かしていた。
地上は重力が重い。当たり前のその重さが、今はもどかしく感じる。
医務室は、あと何区画先だった。
どうしてこんなにも俺は焦っているのだろうか。
冷静に考えれば思いつく疑問も、今は出てこない。
召集の理由は次のミッションについてだが、向かう先はそれとは違う理由だった。
あの男が怪我をした、ということだった。
ミッションはコンプリート。さすがだと思ったが、その報告に目を通しているうちにそれだけではいられなくなった。
詳しい話は聞いていない。ただ、あの男が負傷したのだという話で、報告書はそれが中々に酷いものではないかという推測がたった。
それでどうして俺がこんな風に走っているのか酷く疑問だ。何が俺をこんな風に駆り立てるのだろう。
それでも足は止まらなかった。
暗い世界。
血溜まりと、可笑しな方向へ曲がった腕。冷たい体。そんなものが思考を埋めた。
誰かが居なくなってしまうかもしれないその恐怖が、俺の足を動かした。
ぜーぜーと整わない息を整える間も取らず、ノックもせずに扉に手をかけ、そのまま横にスライドさせる。
自動で開くはずの扉は、無理やりなその動作できしんだ音を立てながら開いた。
「ロックオン!」
機敏な動きでその顔が動く。
いつものように、男は笑わなかった。どうした、とも言わなかった。厳しい顔をしたまま何も言わなかった。
沈黙が流れる。吐く息の荒さが際立つ静寂。
それを破ったのは、男の警戒したような立った一言だった。
「誰だ」
低く、低く、問う声。
冗談ではなかった。男の顔を見ればそれが分かった。
”頭に強い衝撃を受けたと思われる”
報告書にあった一文を思い出す。
最悪ではなかった。それでも、喪失感が思考を埋め尽くす。
ただ、この男に知らないといわれただけでこれはなんだ。
まるで急速に色を失くす。
色鮮やかなはずの花の色も、服の色も、男の瞳の色すら。
世界が、こんなにも色がないのだと初めて知った。
02. 忘却者の問
飛び込んできた子供の姿に混乱した頭はさらに疑問符を投げる。
呆然としたような顔。
それから妙に泣きそうな顔をして静かに出て行った。
「なんだぁ?あいつ……」
分からない。記憶に無い。記憶が、無い。
だというのにあの傷ついたような瞳にわけのわからない罪悪感を覚える。
(なんだって言うんだ……)
理不尽だ。記憶がない事で傷つくべきは自分であるはずだ。
不安で、呆然としているのは記憶が無いほうだ。今まで生きてきた土台が無くなったということなのだから――――敵も見方も区別が付かない。
実際不安ではあった。だがどうにかなるとも思っていた。
どうにかなる。どうにかできる。自身の能力への信頼。
それはあった。
生きていくための力は失われていない。言葉も喋れるし、手足も動く、部屋の中にあるものの使い方など日常的な知識であれば分かる。
分かる、というよりは体が覚えているという方が正しいのか。
今度は軋んだ音も無く扉が開く。
そういえばあのガキは手で無理やり開けて入ってきたのだ。笑ってしまう。ほんの少し待つだけで開く自動扉であるというのに。
何を急いでいたというのか。
(俺のことが心配だった?)
まさか。そんなわけがないだろうと思う。根拠は無かった。何故か自然にそう思う。
それを俺はあのガキと自分に何か接点があるようには見えないからだと思った。
「ロックオン・ストラトス」
それが自分のことを示しているのであると、さすがに分かる。
入ってきたのは今度は妙齢の女性だった。
目が覚めてからすでに一度会っている。ドクターに指示を出していた肉感的な美人だ。
豊かな胸に目がいってしまうのは男として当然のことと言っておこう。
「あのガキはなんだ?」
「ガキって…・・・」
訝しげな顔をして、それから美人ははっと息を呑んだ。
「刹那が来たの?」
驚いたような顔はやはりあの子供が此処へ来ることはかつての俺とあいつを知る人間であっても予想外ということだ。
あの子供は刹那というのか。
刹那、セツナ、せつな。その響きに呼び起こされるものはない。
やはり知らない。
「さてね。刹那といわれても誰のことだか」
「黒い髪と赤い瞳の十六歳の子よ」
確かにそんな色をしていた。
だが……
「十六歳?なら違うな。もっと小さかったぜ」
「いいえ十六歳よ。東洋人は少し年より幼く見られるし、彼は少し……小柄なの」
つまり成長過程に色々あったということなのだろう。
十分な栄養が取れずに未発達ってところか。生まれが貧しかったのかもしれない。
「あんたもそうだって?」
「”東洋人は”というところならそうよ」
「けど女性は若く見られた方がいいんでしょう。ミス・スメラギ?」
彼女が息を呑む。前も俺はこの人のことをそう呼んでいたんだろう。
でもそんな呼び方は一般的なものでしかなく、記憶が戻ったわけじゃない。戻ったのだと錯覚するのは勝手だが、そんな期待は重いだけだ。
そのことを彼女も分かっているのだろう。首を一度振ってから意識を切り替えたように真っ直ぐに見てくる。
「刹那・F・セイエイ」
一度、言葉を切る。
重々しいまでに大切に告げられたその名前はさっきのガキのものなのだろう。
呆然とした顔が再び浮かぶ。
赤い瞳に浮かんだ困惑と失望に、だからなんでおまえがそんな顔をするんだと苛立ちながら続きを待つ。
あのガキの情報は頭の中から出てこなければ俺には彼女に聞くしかない。
どうしてあんな顔をしたのか、どうして俺が罪悪感など感じなくてはならないのか。
その理由も関係性も。
「貴方が守りたかったガンダムマイスターよ」
守りたかった、という言葉は分かる。俺があのガキをというのはまったく実感できないが、あのガキが可愛らしく見えずとも子供であるということで一応は納得できる。
ただ。
”ガンダムマイスター”
おそらくは何かの地位か呼称なのだろうけれど。
それすらも俺には未知の言葉だった。
03. 掌の上の夢
ロックオン・ストラトスはミッションで負傷、確かにそのミッションはコンプリートされたが任務続投は無理。
次のプランもすでに下っていたのだが、現状そのプランの施行は無理だ。変える必要があった。
故に集合を掛けたブリーフィングルームの中にガンダムマイスターの数は2つ。
一際小柄な少年の姿が無い。
「あれ?」
仕方ないわね、と口にする。
甘やかすわけじゃない。けれどあの状態のロックオンに会ったのなら仕方がないと思う。
なんだかんだ言っていてもやはり刹那はロックオンに心を許していた節がある。ショックは大きいだろう。
いつだって、どんなに邪険にしたって、ロックオンは刹那に話しかけるのを止めなかった。
刹那にすれば大きな手でぐしゃぐしゃと頭を撫で回して、兄貴分のつもりでロックオンは色々世話を焼いていた。見ているほうからすれば微笑ましい遣り取り。
けれど先程の彼のあの反応は。
首を振る。
仕方のないことだ分かっている。だが警戒心を露にしたロックオンの対応は、きっと刹那を傷つけただろう。
「誰か刹那を呼んできてくれるかしら」
端末にもう一度呼び出しを流してもおそらく伝わりはしないだろう。
同じ施設内に居るのであれば誰かが呼びに行った方が早い。
「……私が」
「フェルト」
手を挙げた少女に少し驚く。
彼女もまた、記憶の無い彼にとても懐いていた子供だ。そして刹那と同様に感情をあまり表に出せない子。オペレーターであるから話すことはするが、話しかけることは得意なほうではないはずなのに。
「多分、分かるから……」
私はまだ会っていないけれど、きっと忘れられたら悲しい。
そう言うフェルトの言葉は心を打つ。
仕方ないと割り切れない。子供たちは悲しみを唯一共有できるのかもしれない。
*
記憶の無い人間はえてして不安になるという。
不安定な精神を支えてやるのが周囲の人間のあり方だ。
分かってはいた。だが……あの男の顔を見て、声を聞いて、そして『誰だ』と誰何する声。厳しい顔。
あんなものを向けられた事は無かった。
思い出すと胸が痛い。そばに居るのが辛い。
鬱陶しい、でも嫌いじゃなかった。いつだって言うことは間逆のことだったけれど、あいつは気にしなかったし、ある程度は分かってくれていたのだろうと思う。
だからそんな日がくるなんて思わなかった。
あいつになら触れられることも嫌いじゃなかったのに。
コール音。
誰だろうか。あの男だろうか。
嫌だと思ってぎゅっと布団を握り締める。
だがいつまで経っても開かない扉に疑問を覚る。
いつもならハロの解除機能でロックを解除して許可無く入ってくるのに。
「刹那?」
「フェルト・グレイス」
迷いながらもやっと布団から手を放し、扉を開けてそこに居た人物に目を見張る。
どうして彼女が。
初めての事だ。ロックオン・ストラトス以外がこの扉を開くことなど。
「ミッションが始まる」
「え……」
端末を確認しようとして身に着けていないことを知る。
失態だ。
いつから端末を持っていなかった。いつ召集が掛かった。
「ブリーフィングルームに集合」
何をやっているのかと思う。
こんなことくらいで。こんな、醜態を晒すなんて。
「すまない」
「いい。刹那はロックオンが好きだもの」
仕方ないよとフェルトは口にする。
彼女もそういえばあの男と話しているのをよく目にした。
あの男はきっと子供に優しいのだ。自分が子ども扱いされていたことは知っている。
だから彼女も同じ。
喪失の痛みを知っている。
04. 漆黒に踊る
ブリーフィングルームにはもう他のガンダムマイスターが揃っていた。
当然そこにロックオンの姿はなく、そのことが妙に胸に突き刺さる。
今回のミッションはデュナメスは無しで行うのか。
不安とは違う、その感慨は寂寥感とでもいうのか。寂しい、そんなことを思う自分を叱咤する。
「刹那。ミッションよ」
遅いとは言わなかった。
スメラギ・李・ノリエガは端的に命令を下し、刹那を迎え入れた。そのことに安堵してフェルトから離れ他のガンダムマイスターたちの側へと位置を取る。
どうして遅れたのか。気づかなかったなんてそんな失態を口にすることは憚られた。
失態を報告するだけならいい。
だが……
この状況で、変な勘ぐりをされることが嫌だった。
別に、あの男のことなどなんとも思っていないのだと、気を使う必要などないのだと。
「人革連の軍事演習の調査に向かうわ」
ミッションは明白だった。
調査というが、つまりはどの程度の戦力があるのか叩いて確認するということだ。意味は殲滅に近い。
ガンダムが近づけば電波障害が起こる。それは相手も分かっているからガンダムは単純に遠くから見るだけの任務には使えない。
―――デュナメスの狙撃用ライフルのスコープと、その視野を使えるロックオンでなければ。
それはロックオンが次に当たるはずの任務だったのだと、それを示していて。
その事実にまたどこかが軋んだ。
*
パイロットスーツに着替え、エクシアに乗り込む。
いつも通りの場所に位置した機体へ。無意識の行動。
「エクシア、介入行動に入る」
レバーを握り、ペダルを踏み込む。
誘導に従い、プライオリティを書き換え、宇宙空間に飛び出せば暗いソラが広がる。
黒い、空間。黒い、空。
遠くに星があり、時折何かの破片が見えるのが常だが、見回す限りどれも同じに見える。
(なんだ……?)
違和感。
だが暗い宇宙の中で色を見分けることは難しい。
「あれか」
今回のミッションポイントまで到達し、センサーを見るがそこでも反応が悪い。
読み取れないわけではないが、いつものような赤い反応はない。白い文字が見えるだけだ。
(故障か?)
そんな筈はない。十分に整備されているはずだが、システムのバージョンアップでもしたのか?
ロックオンの事でデュナメスの修理が大変だっただろうから導入したあとテストをする時間がなかったのだろうか。
とりあえず帰ったらイアンに聞く必要がある。
『刹那、あのピンクの機体を』
ピンク?
どれだどれだどれだ。
周りを見回しても白と黒しかない。
ピンクのモビルスーツなんてそんなものと思ってふと、一機他とは形の違うものを発見する。
黒より少し色が薄い、灰色。周囲のティエレンよりも薄い。
待て。
宇宙型ティエレンの色は黒に近い青だ。紺とも言えるが、完全に黒と間違える色でもない。
だが事実そこは黒と白の世界だ。
つまりそれは―――色が、無い。
宇宙の色も、センサーの色も、ティエレンの色も。
可笑しいのはそのものではない―――自分の方だ。
気づいた瞬間。
「あぁぁぁぁぁぁぁ」
脳が、認識を拒否した。
05.喪失の爪痕
破壊の後が色濃く残る宙域を離脱して、プトレマイオスはラグランジュポイントを航行する。
その船橋にミッションに出ていたガンダムマイスターのうち二人が飛び込んできたのは、作戦を終え僅か数分の出来事だった。
「刹那は?」
「閉じこもってるわ……」
アレルヤの言葉にスメラギは首を振って答える。
むちゃくちゃに暴れだしたエクシアを操った少年は、着艦後すぐに姿を消している。尤もその所在は個人に与えられた部屋の中に確認されているが。
本来の任務は人革連の軍事演習の調査だ。しかしキュリオスとヴァーチェの任務はむしろ暴れるエクシアの押さえが中心となった。
モニターに映し出された戦闘記録はエクシアが我武者羅に剣を振るう姿がある。そこにミッションプランの影はない。
盲目に、目標だけではなく全てを破壊しつくそうとした姿が目に映る。
「刹那の暴走癖にも困ったものねぇ」
重くなる空気を察してクリスティナは仕方ないんだからと言ってみる。それに同意して乗っかって、それ以上重い雰囲気にならないようにと会話を続けようとしたリヒテンダールは言葉を発する前に遮られた。
「あれは暴走ではない」
ティエリアが否定した。
冷たい顔と声でありながら、言葉は刹那を擁護しているようにも取れる。
「多分……識別できなかったんだ」
「識別できない?」
でも刹那に怪我をしている様子は無いというクリスティナの疑問に、ティエリアはやはり淡々として答える。
「識別できないのは色彩だけだ」
色の無い世界。
それまでの世界から唐突に切り替わった。新たな認識をしようとして気づいたが故に。
エクシアが暴走を始めたのはピンクのティエレンを破壊せよという命令が下ってからだ。
色を意識しようとして、そしてふと気づいてしまったのだろう。
世界に色が無いことに。
「刹那・F・セイエイの瞳にはモノクロにしか世界は映っていない」
ティエリアの言葉は推測であったが、一番事実に近い推測であった。
だがその推測は、刹那の戦闘員としての、つまりはガンダムマイスターとしての生命を奪う事実に他ならない。
フェルトがブルリと身を震わせる。その想像は、酷く刹那に残酷だ。
あんなにもガンダムを、エクシアを必要としている人が。
クリスティナが否定を求めるようにティエリアに食いつく。
「でもこの前まで刹那はちゃんとやってたじゃないっ」
「精神的ストレスにより、色彩を感知できないなど視覚は異常をきたす事がある」
精神的ストレス。
それに思い当らない人間など此処には居ない。何を言われたのか、何があったのか。
知ることはないが、刹那がミッションに気づかないほどに動揺する出来事があった。
「ロックオンのこと、それだけショックだったんだね……」
「一人が倒れたら共倒れか?まったくこれだからガンダムマイスターに相応しくないんだ」
アレルヤが口にした痛ましげな、けれど微笑ましげな理由にもティエリアは容赦無い。それは余剰酌量の理由にはならない。
「そう言うティエリアが一番心配してるみたいよね」
ニンマリとスメラギが笑う。
綺麗な顔がヒクリと不機嫌そうに歪んだ。
「気づいたのはあなただけでしょ?」
「馬鹿なことを。あなたも当然気づいていたはずだ」
「まぁ予測は、ね」
ミッション前に出来なかったのが残念だわと肩を竦めるスメラギに、確かにそうだとティエリアも肯く。
その事態さえも予測し、戦略を立てるべきだったのだ―――戦術予報士であるのなら。
「それよりこれから当面どうするかよね。刹那がいつ回復するか……」
「元々あの子供には適正などない」
「それはあなたが決めることではないわ」
回復を待つ必要などない。変えてしまえというティエリアにスメラギはその意思が無いことを示す。
彼の信じる唯一という伝家の宝刀を引き合いに出して。
「ヴェーダは、あの子をガンダムマイスターに選んだ。それはあなたも知っているはずよ」
知っている。
知っていてなお、ティエリアは疑問を抱かずにはいられない。否定をせずにはいられない。
適正の無い人間が乗り続ければ死は簡単に訪れるだろう。
「だが危険すぎる」
そんな脆弱な精神なら。
子供だから仕方ないなどと言える世界ではない。ここは……我々は。
世界を敵に回し、変える存在なのだから。